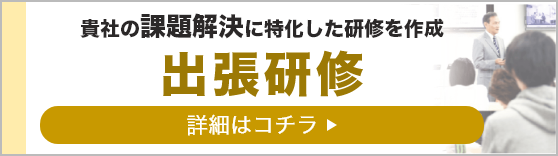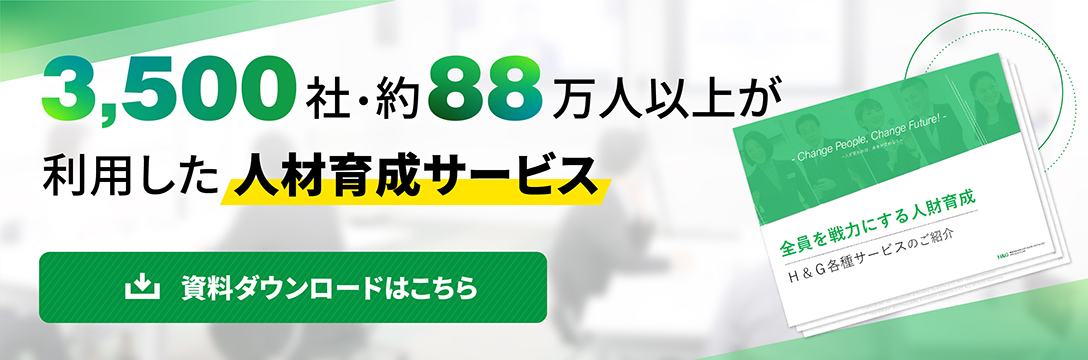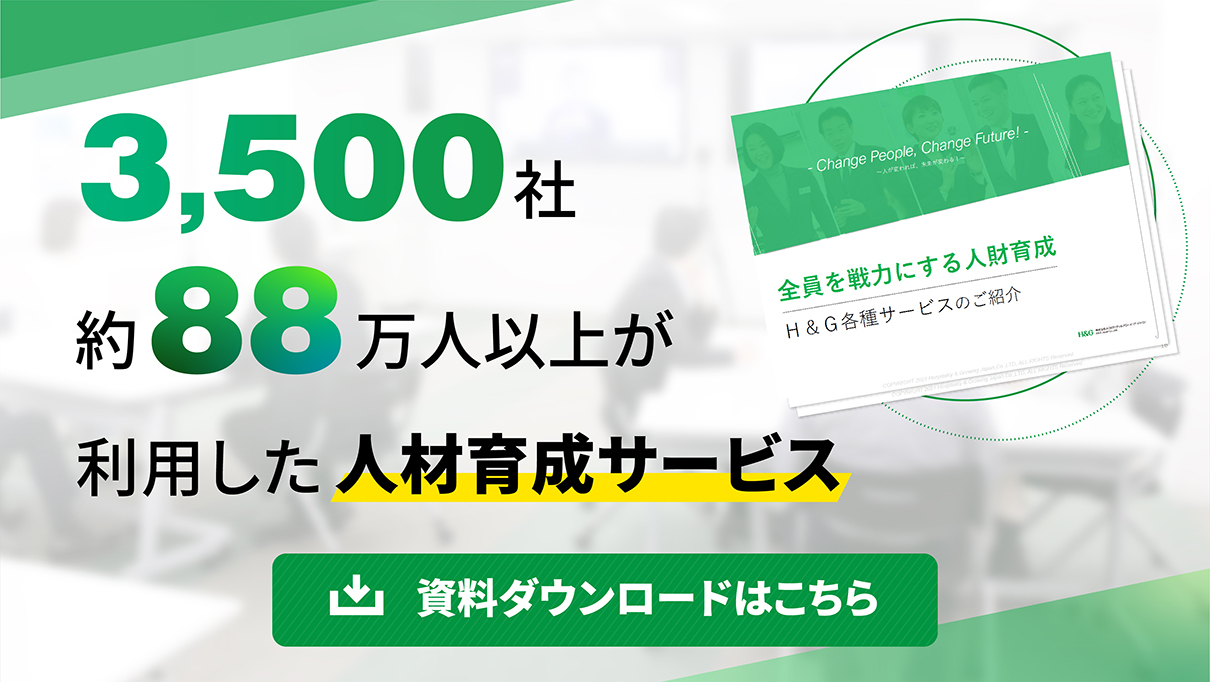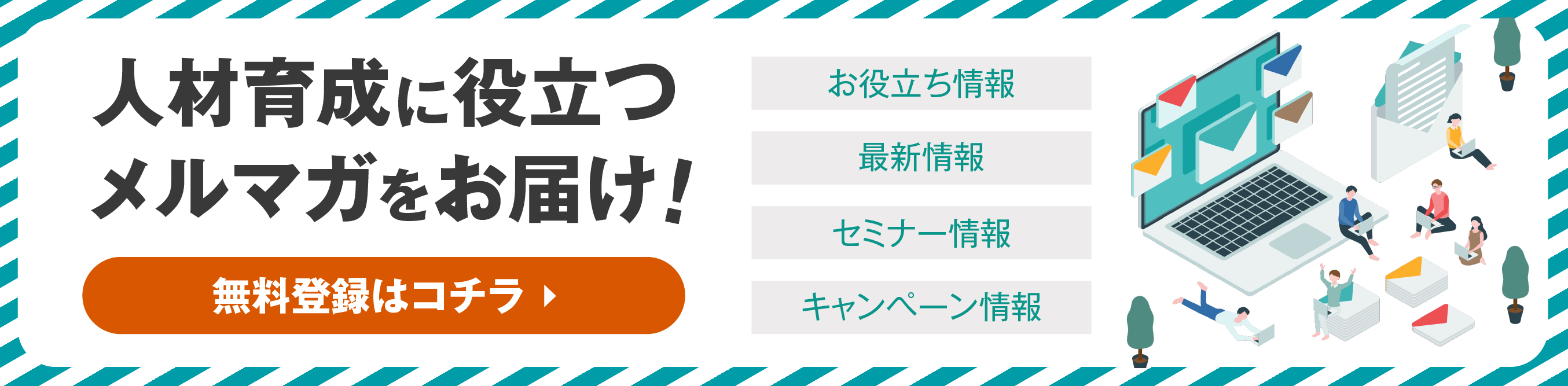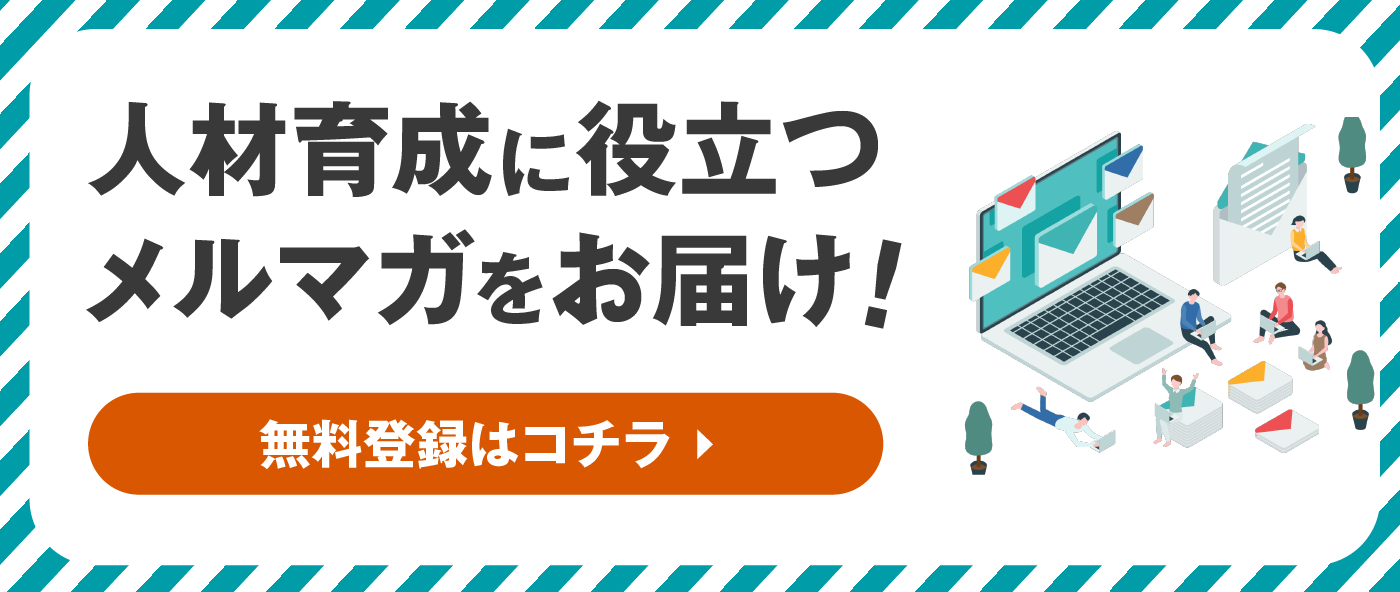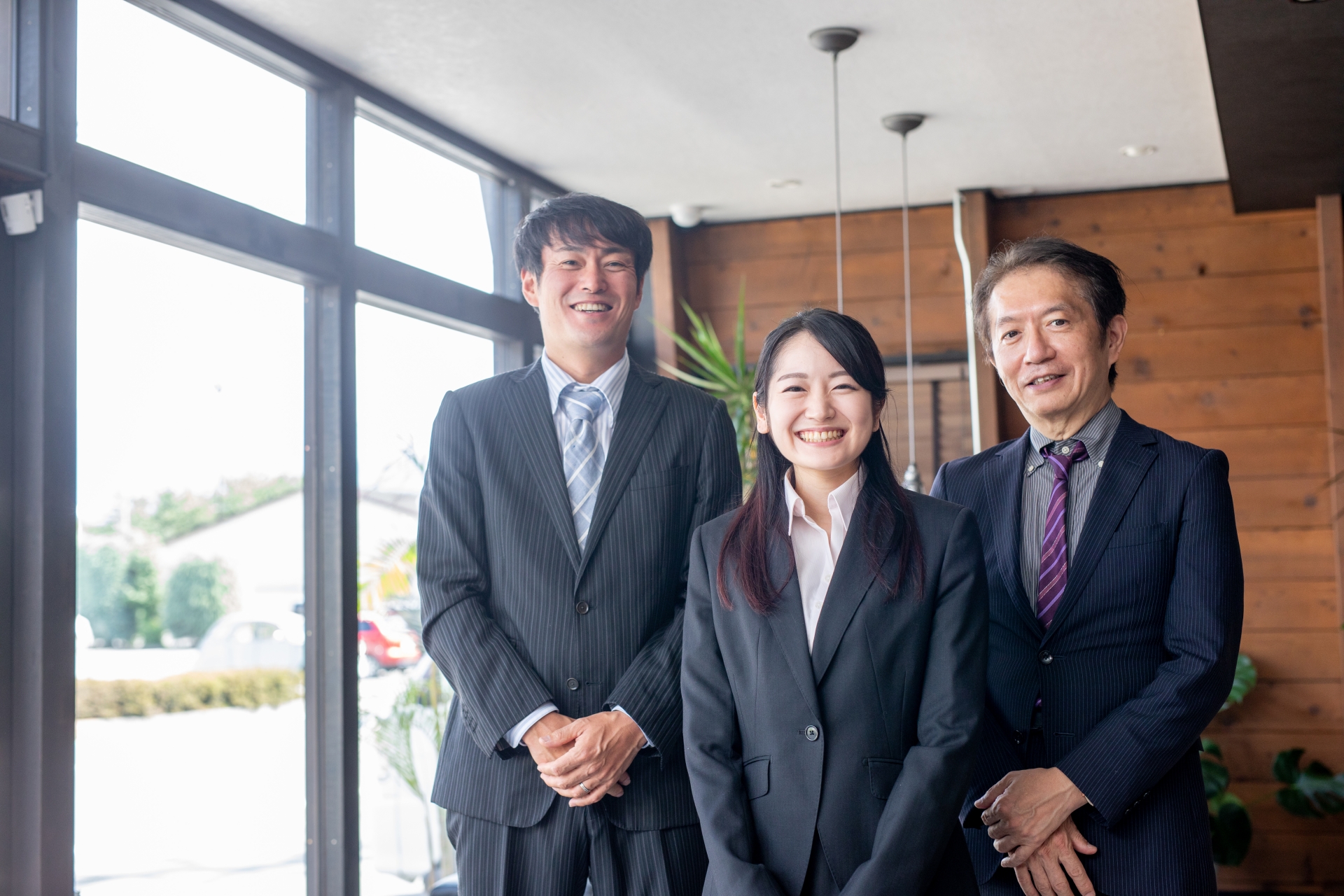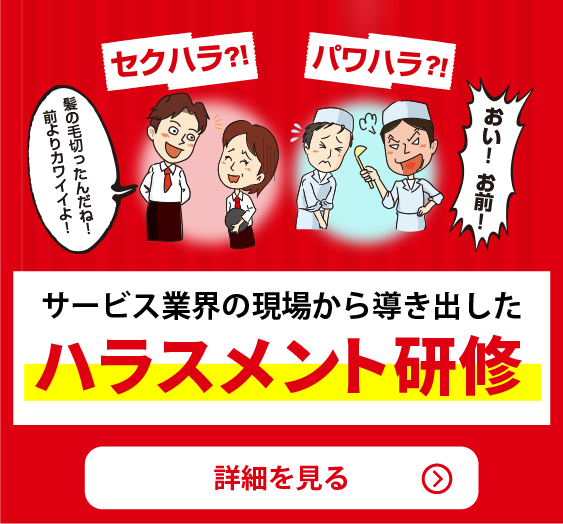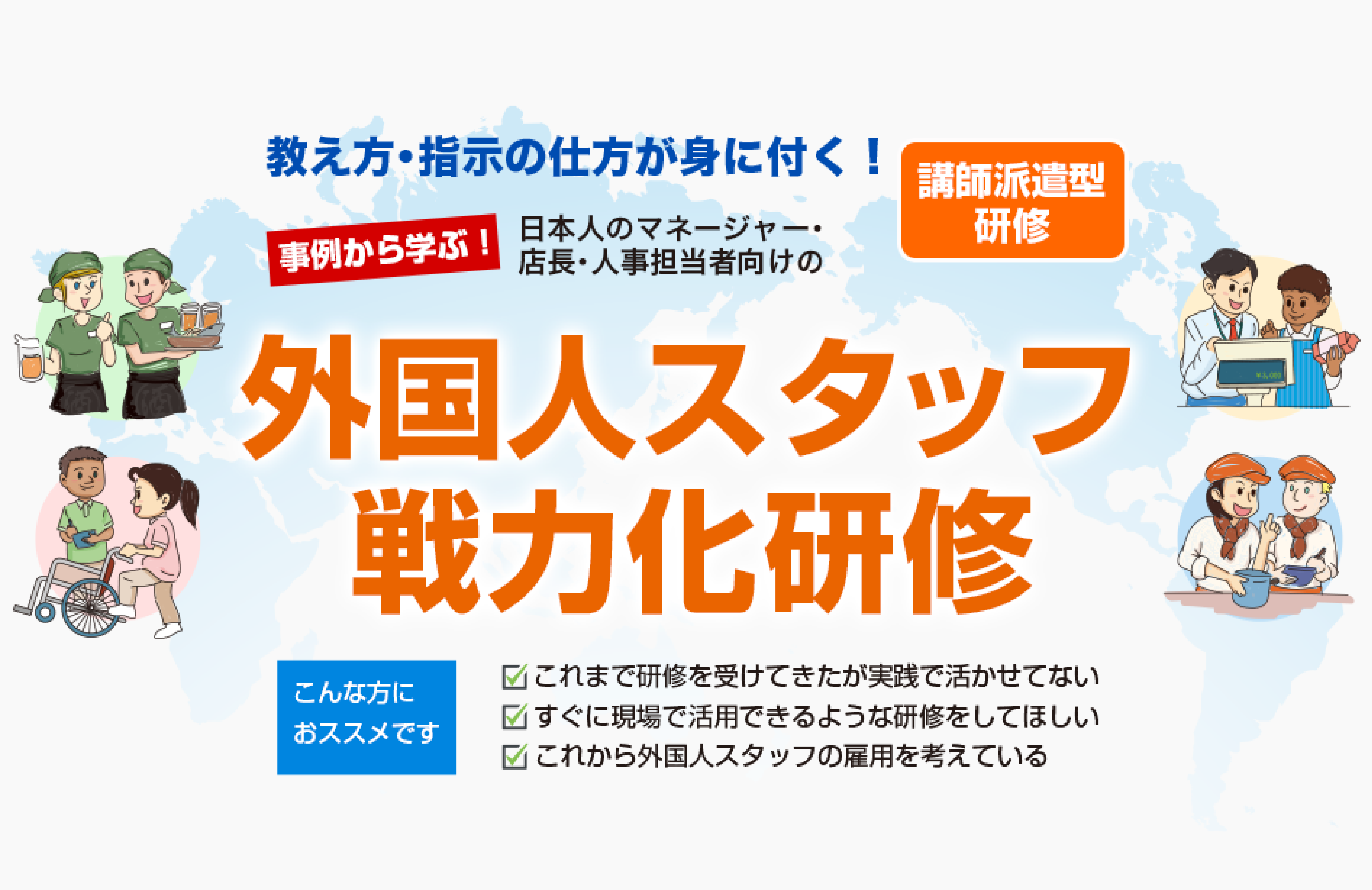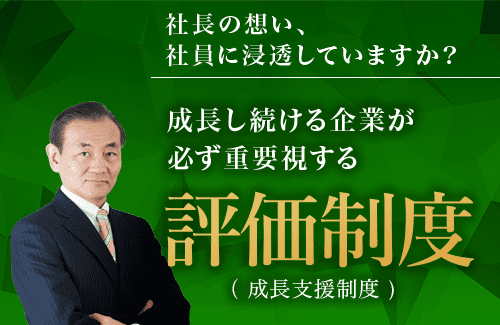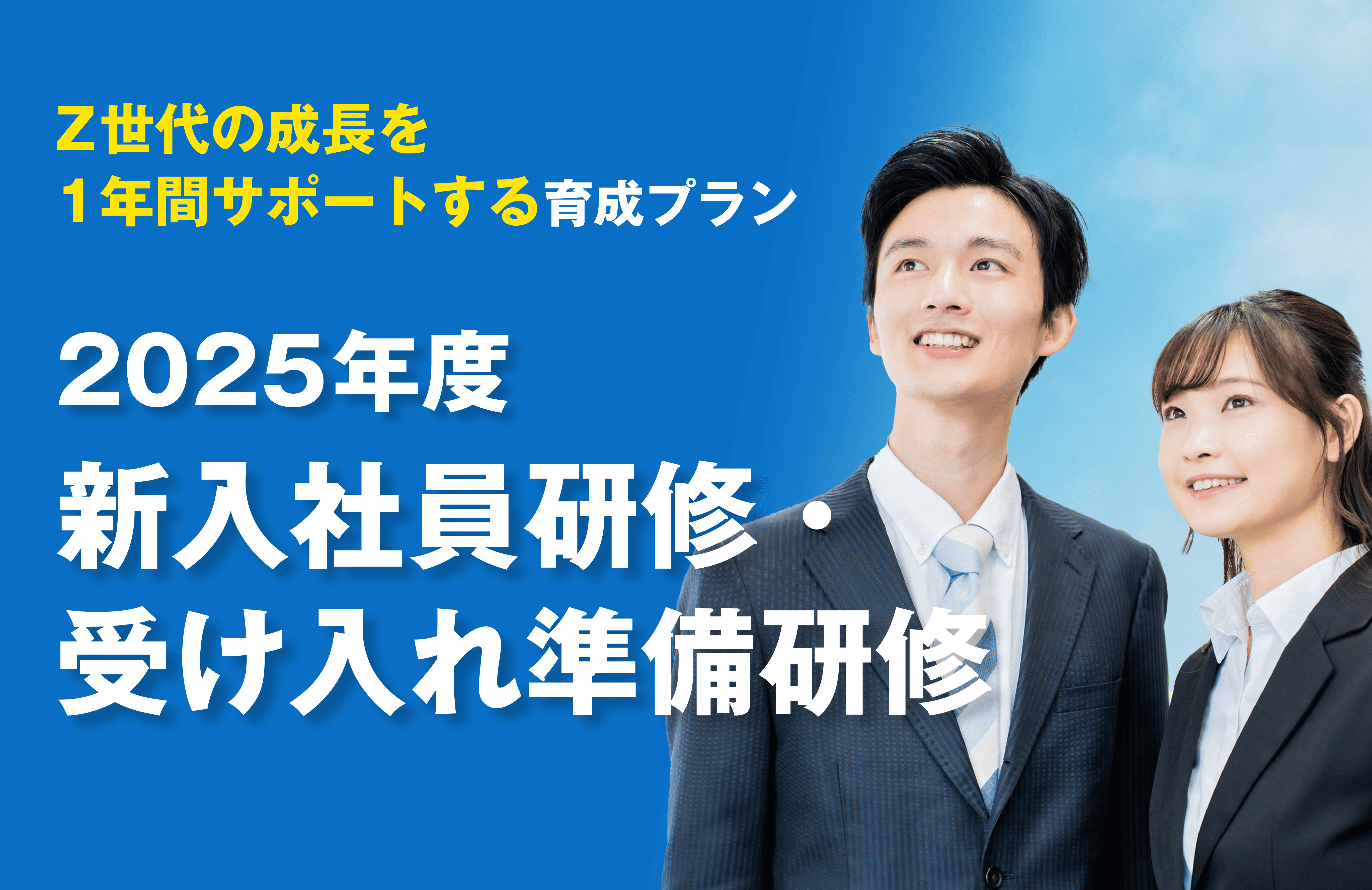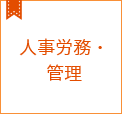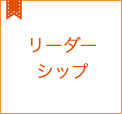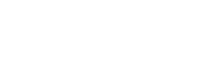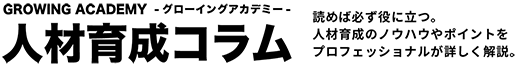- Home
- お役立ちコンテンツ, 離職防止, ニュース(人財/人事関連)
- ワークライフバランスが整う企業とは?制度設計や成功事例を解説
ワークライフバランスが整う企業とは?制度設計や成功事例を解説
- 2025/5/16
- お役立ちコンテンツ, 離職防止, ニュース(人財/人事関連)

目次 こちらをクリックすると詳細を表示・非表示できます
- 1.なぜ今、企業にワークライフバランスが必要か
- 2.ワークライフバランスの定義と変遷
- 3.ワークライフバランス推進の企業メリット
- 3-1.従業員満足度・エンゲージメントの向上
- 3-2.生産性の向上
- 3-3.離職率の低下と人材確保
- 3-4.企業イメージ向上
- 3-5.コスト削減
- 4.企業の具体的な取り組みと制度設計
- 4-1.勤務形態の柔軟化
- 4-2.休暇制度の充実
- 4-3.労働時間の適正化
- 4-4.育児・介護支援・その他
- 5.先進企業のワークライスバランス事例紹介
- 6.国や自治体による支援・認定制度の活用
- 7.社内で制度を機能させるための実践ポイント
- 7-1.導入目的と運用方法の明確化
- 7-2.経営層の関与とメッセージ発信
- 7-3.現場の声を反映し、定期的な見直しを実施
- 7-4.KPIなどで可視化し、評価基準に組み込む
- 8.IT・DXによる効率化とワークライフバランスの推進
- 9.まとめ:ワークライフバランスは経営戦略である
1.なぜ今、企業にワークライフバランスが必要か
現代の日本社会では、働き方改革や少子高齢化、ダイバーシティ推進などを背景に、従業員一人ひとりの価値観が多様化しています。これまで「長時間労働が美徳」とされた風土から脱却し、企業が積極的にワークライフバランス(仕事と生活の調和)を実現する必要性が高まっています。
ワークライフバランスは、企業の魅力を高め、優秀な人材を確保・定着させるための重要な経営戦略でもあります。本記事では、定義、制度、導入事例、国の支援策などを網羅的に紹介し、読者が自社に活かせるヒントを得られる内容を目指します。
2.ワークライフバランスの定義と変遷
一般的に「ワークライフバランス」とは、仕事とプライベートの時間を適切に配分し、どちらも充実させることを指します。
東京都では「ライフ・ワーク・バランス」という言葉が採用され、生活を起点とした働き方の再設計が重視されています。さらに近年では「ワークライフインテグレーション」や「ワークライフマネジメント」といった、より柔軟で個別最適化された働き方の概念も登場しています。
重要なのは、単に私生活を優先することではなく、「仕事と生活の相互向上」を目指す考え方です。
3.ワークライフバランス推進の企業メリット
企業がワークライフバランス施策を推進することで、次のような効果が期待できます。
-
・従業員満足度・エンゲージメントの向上
・生産性の向上
・離職率の低下と人材確保
・企業イメージ向上
・コスト削減
3-1.従業員満足度・エンゲージメントの向上
生活が充実することで、従業員は心身のバランスが整い、仕事へのモチベーションが向上します。仕事に対する意欲が高まることで、エンゲージメントの高い組織が形成され、離職のリスクも低下します。
3-2.生産性の向上
ワークライフバランスが整うことで、業務に対する集中力が高まり、効率的に仕事を進めることが可能となります。結果として、短時間でも高い成果を上げる「高生産性の働き方」が実現します。
3-3.離職率の低下と人材確保
育児や介護と両立しやすい環境を整備することで、多様な人材が長く働ける企業となります。これにより、離職率が下がり、人材の定着や新規採用への好影響が期待されます。
3-4.企業イメージ向上
制度を整えるだけでなく、実際に活用されている企業は、社会的に「ホワイト企業」として認知されやすくなります。企業イメージの向上は、採用活動や顧客との信頼構築にも寄与します。
3-5.コスト削減
残業代や医療費、採用・教育コストの削減が期待されます。健康的な働き方の浸透により、メンタルヘルス不調による休職も減少し、結果として企業経営の安定化にもつながります。
4.企業の具体的な取り組みと制度設計
ここでは、企業の具体的な取り組みと制度設計をご紹介します。
-
・勤務形態の柔軟化
・休暇制度の充実
・労働時間の適正化
・育児・介護支援・その他
4-1.勤務形態の柔軟化
働く時間や場所の自由度を高めることで、従業員の生活スタイルに合った働き方を可能にするのが、勤務形態の柔軟化です。テレワークや在宅勤務の導入は、通勤時間の削減と家庭との両立支援に貢献します。
また、フレックスタイム制度やスーパーフレックス制度により、ライフステージや生活環境に応じた働き方の選択ができるようになり、社員の自立的な時間管理を促します。さらに、短時間勤務制度は育児や介護と仕事を両立したい従業員にとって、安心して働ける制度として注目されています。
4-2.休暇制度の充実
多様なライフイベントに対応するため、企業は休暇制度の見直しと整備を進めています。育児休暇や介護休暇、看護休暇、アニバーサリー休暇などは、家庭や個人の事情に寄り添った働き方を実現するものです。また、年次有給休暇の取得を奨励し、その取得率や消化率を可視化することで、制度の形骸化を防ぎます。さらに、リフレッシュ休暇やフリーバカンス制度など、心身をリセットし業務への再集中を促す休暇制度も注目されています。
4-3.労働時間の適正化
労働時間の適正な管理は、従業員の健康を守るうえで欠かせません。ノー残業デーの導入や、勤務時間の可視化と管理は、過度な労働を抑制し、生産性の向上にもつながります。さらに、残業チケット制度やサービス残業の禁止徹底など、制度的・運用的な工夫を取り入れることで、企業全体での労働時間の是正と意識改革が促進されます。
4-4.育児・介護支援・その他
ライフステージに応じた支援制度の整備は、従業員の長期的な活躍を支える重要な要素です。社内保育園や授乳スペースの整備により、育児中の従業員も安心して働くことができる環境が整います。また、副業や自己投資支援制度、再雇用制度の導入により、キャリアの選択肢を広げながら継続的に働ける仕組みを構築。さらに、従業員支援プログラム(EAP)やメンタルヘルス対策の充実は、心身の健康維持を支援し、安心して働ける職場環境の実現に寄与します。
5.先進企業のワークライスバランス事例紹介
ここでは、先進企業のワークライフバランス事例をご紹介します。
-
・株式会社ICJ
・株式会社QOOLキャリア
・株式会社パーキングマーケット
5-1.株式会社ICJのワークライフバランス施策(東京都認定)
株式会社ICJは、「一人ひとりのライフスタイルに応じた柔軟な働き方」を実現するため、フレックスタイム制やリモートワークを導入しています。また、年次有給休暇の計画的取得を促進し、家庭やプライベートの時間を大切にできる環境づくりを推進。若手社員の早期離職防止や定着率向上にもつながっており、全社的な意識改革にも成功しています。
参考:メンタルヘルスの4つのケアってなんだろう?(厚生労働省)
ライフ・ワーク・バランスEXPO東京_株式会社ICJ(東京都)
5-2.株式会社QOOLキャリアのワークライフバランス施策(東京都認定)
QOOLキャリアは、社員一人ひとりが「人生もキャリアも前向きに歩める」よう、ライフイベントに応じた柔軟な働き方を推進。子育て中や介護中の社員も働きやすいよう、フルリモートワークや短時間勤務、時間単位の有給休暇など多様な制度を整備しています。また、対話を重視したマネジメントとチーム連携により、エンゲージメントと組織の一体感を高めています。
参考:
ライフ・ワーク・バランスEXPO東京_株式会社QOOLキャリア(東京都)
5-3.株式会社パーキングマーケットのワークライフバランス施策
株式会社パーキングマーケットは、従業員が安心して長く働けるよう、テレワーク・フレックスタイム制度をはじめとする柔軟な働き方を整備。さらに、有給休暇取得の推進や長時間労働の抑制にも取り組み、働きやすさと成果の両立を図っています。エンジニア職を中心に、男女問わず多様な働き方を実現し、成長意欲の高い人材が定着しやすい環境づくりを実践しています。
参考:
ライフ・ワーク・バランスEXPO東京_株式会社パーキングマーケット(東京都)
地方や中小企業にも独自の施策を展開する企業が増加し、認定企業の事例は「京都モデル」ワークライフバランス推進企業認証制度などでも注目されています。
6.国や自治体による支援・認定制度の活用
政府は「ワークライフバランス憲章」に基づき、誰もが働きやすい社会の実現を目指して各種制度を整備しています。これを基盤とした「働き方改革関連法」によって、長時間労働の是正や柔軟な働き方の選択が企業に求められるようになりました。
企業は下記の制度を活用することで、経済的な支援を得ながら施策を進められます。
-
・「えるぼし」「くるみん」など認証制度の活用
・健康経営優良法人・ユースエール・ホワイト500
・両立支援助成金の活用で経済的負担を軽減
6-1.「えるぼし」「くるみん」など認証制度の活用
「えるぼし」や「くるみん」「ホワイト500」などの認証制度は、企業の働きやすさを対外的に示す強力な証明になります。特に採用や広報の場で企業イメージの向上に寄与し、優秀な人材の確保・定着にも効果的です。
参考:女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)(厚生労働省)
6-2.健康経営優良法人・ユースエール・ホワイト500
「健康経営優良法人」は従業員の健康管理を経営視点で捉える企業に与えられる認定で、大規模法人は「ホワイト500」、中小企業は「ブライト500」に分かれます。また「ユースエール認定」は若者雇用に積極的な企業を評価する制度です。
【参考】
健康経営優良法人認定制度(経済産業省)
非営利一般社団法人安全衛生優良企業マーク推進機構
6-3.両立支援助成金の活用で経済的負担を軽減
「両立支援等助成金」は、育児・介護との両立支援や職場復帰支援を行う中小企業などに対して、一定の条件を満たすことで助成金が支給される制度です。制度導入時の費用補填として有効に活用できます。
7.社内で制度を機能させるための実践ポイント
7-1.導入目的と運用方法の明確化
制度を形骸化させないためには、その導入目的と具体的な活用方法を社員に明確に伝える必要があります。誰のために、どのような目的で導入されたかを共有し、実際の業務に即した運用ルールを整備することで、制度の利用が促進されます。
7-2.経営層の関与とメッセージ発信
経営トップ自らが制度導入の意義を発信することで、社内における取り組みの本気度が伝わります。管理職を含めたリーダー層の積極的な活用とメッセージ発信が、社員の意識改革と制度の定着を後押しします。
7-3.現場の声を反映し、定期的な見直しを実施
現場の社員が感じている制度の使いにくさや課題を把握し、定期的にフィードバックを反映することで、より実効性の高い制度運用が可能になります。導入後の柔軟な改善が、制度定着の鍵となります。
7-4.KPIなどで可視化し、評価基準に組み込む
ワークライフバランス施策の効果を可視化することで、組織全体での取り組み状況を把握できます。有給取得率や残業時間削減などの指標をKPIとして設定し、評価や表彰制度と連動させることで、社内の意識向上につながります。
8.IT・DXによる効率化とワークライフバランスの推進
8-1.勤怠管理・SFA・CRM・RPAで業務効率を最大化
勤怠管理システムや営業支援(SFA)、顧客管理(CRM)、RPAツールの導入により、事務作業の自動化と工数削減を実現。業務の見える化と平準化が進み、生産性向上に直結します。
8-2.Web会議・チャットツールで円滑なテレワークを実現
ZoomやTeams、SlackなどのWeb会議・チャットツールを活用することで、場所を選ばない柔軟な働き方が可能になります。リアルタイムな情報共有と連携で業務効率も維持できます。
8-3.クラウド活用で情報共有と業務の一元管理を推進
Google WorkspaceやMicrosoft 365などのクラウドサービスを活用すれば、部門間の情報共有がスムーズになり、どこからでも業務遂行が可能に。働き方の自由度が高まり、労働時間の削減にも寄与します。
これらにより、労働時間の削減と業務負荷の平準化を図ることが可能になります。
9.まとめ:ワークライフバランスは経営戦略である
ワークライフバランスは単なる制度や福利厚生ではなく、企業文化そのものであり、経営戦略の中核です。従業員一人ひとりの人生を尊重し、持続可能な職場づくりを推進することが、企業の成長にもつながります。
経営層・現場・個人が一体となって推進することにより、企業価値・従業員の満足度・社会的評価すべての向上が実現可能です。
関連するサービス