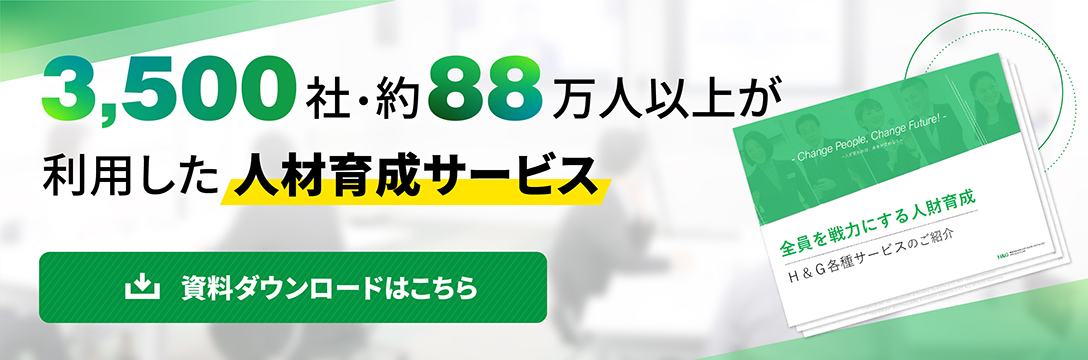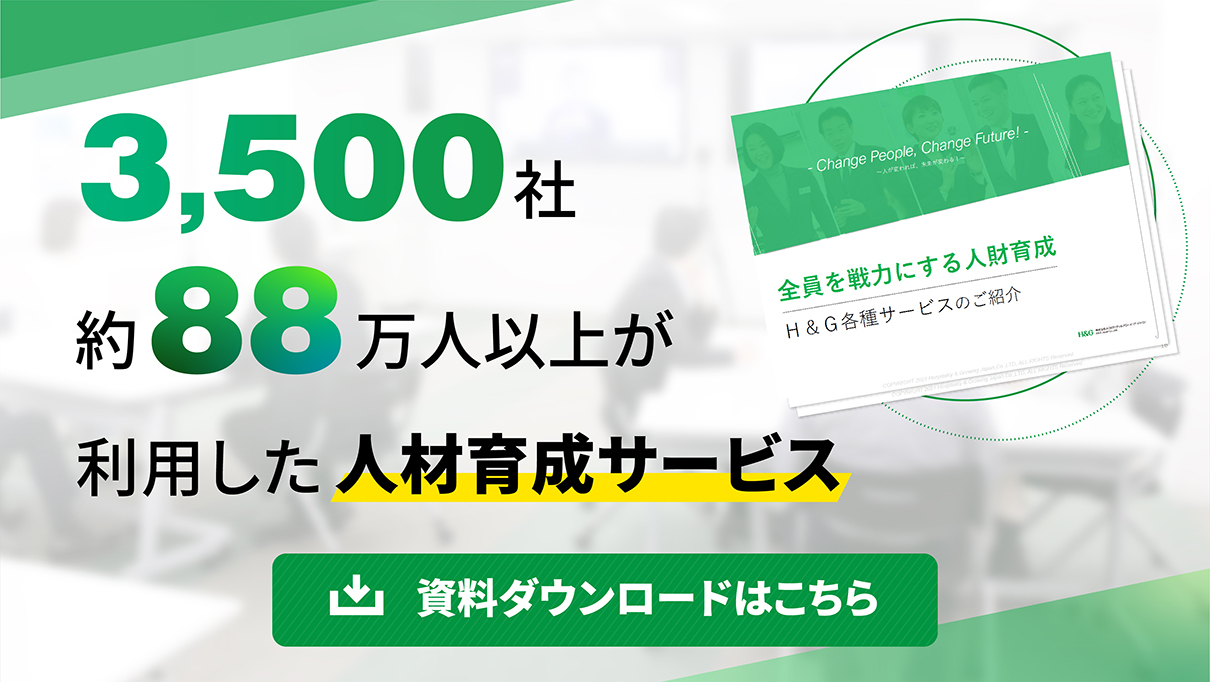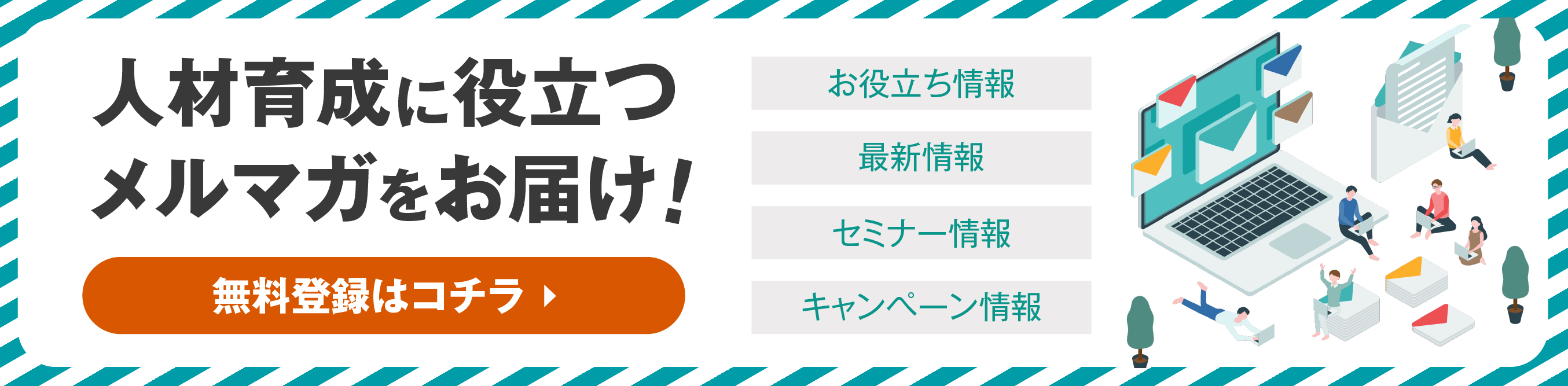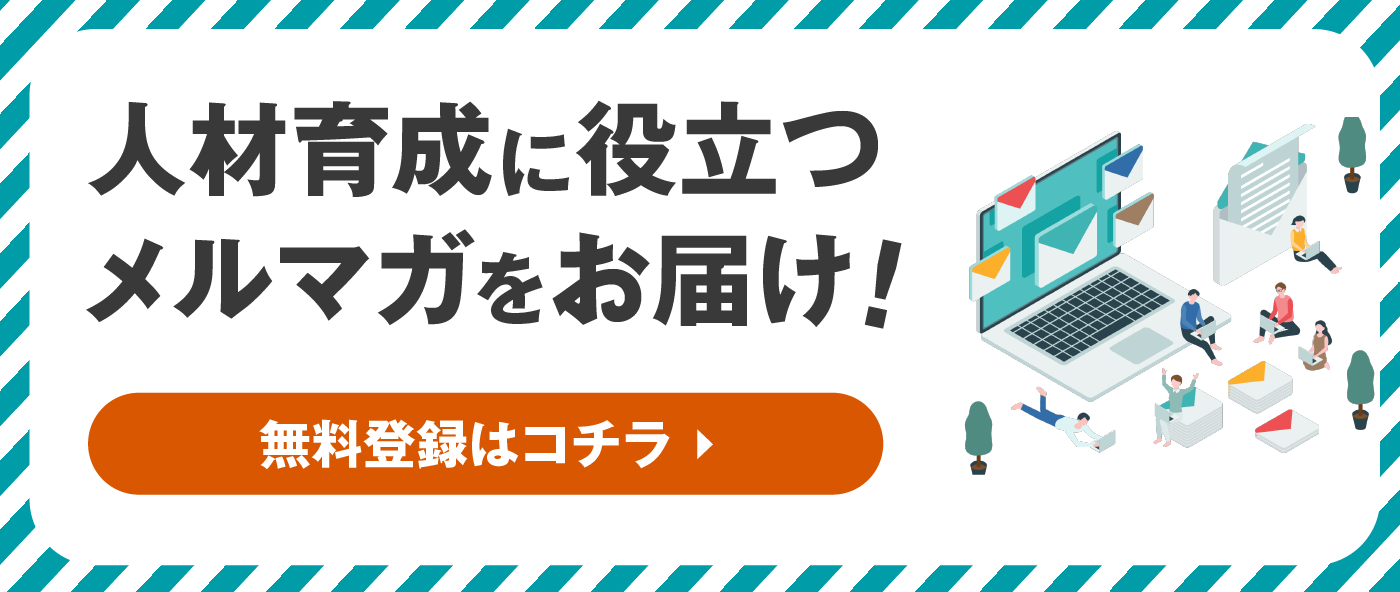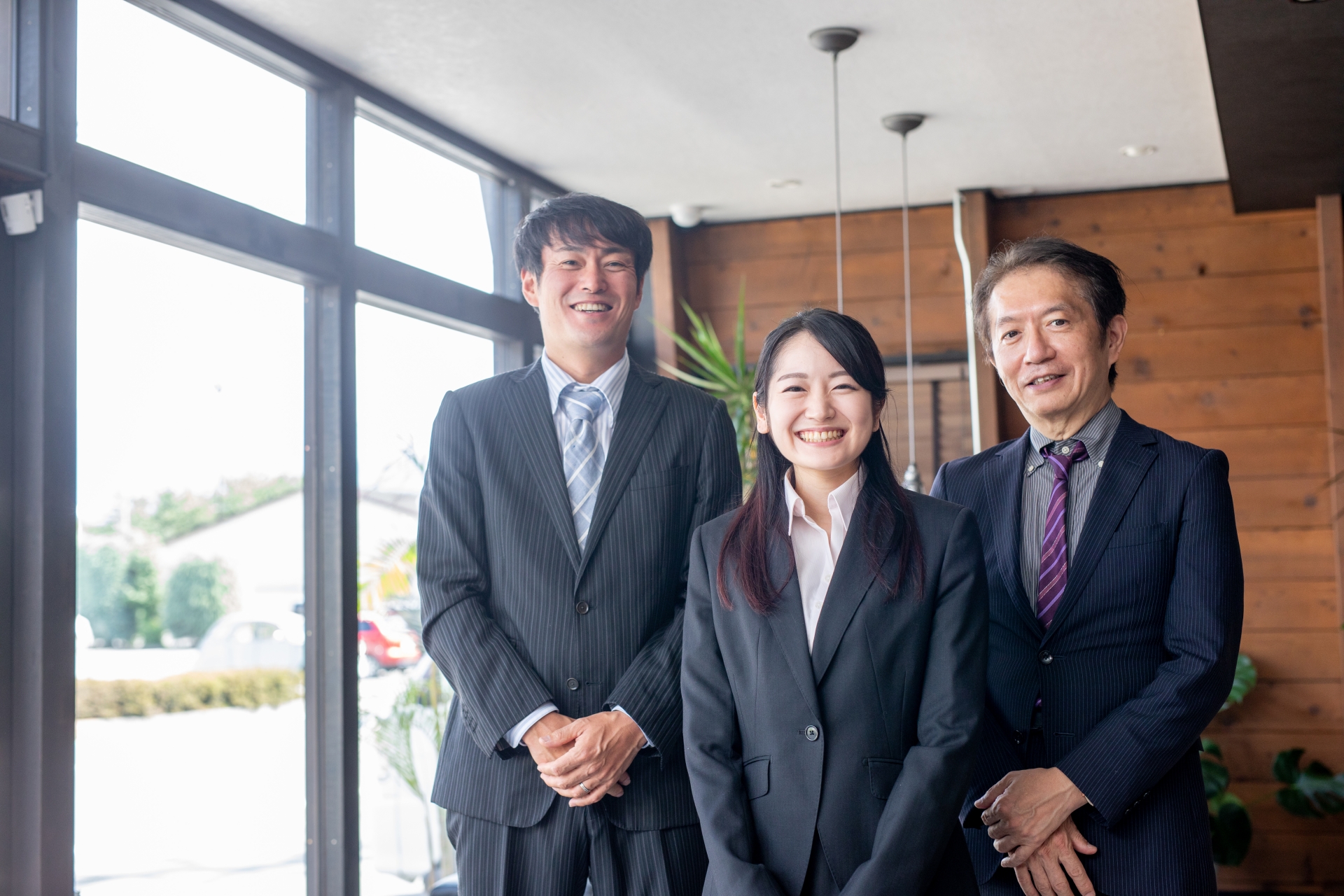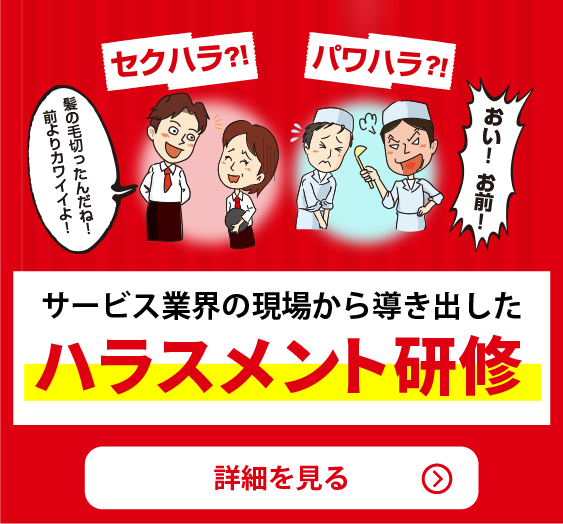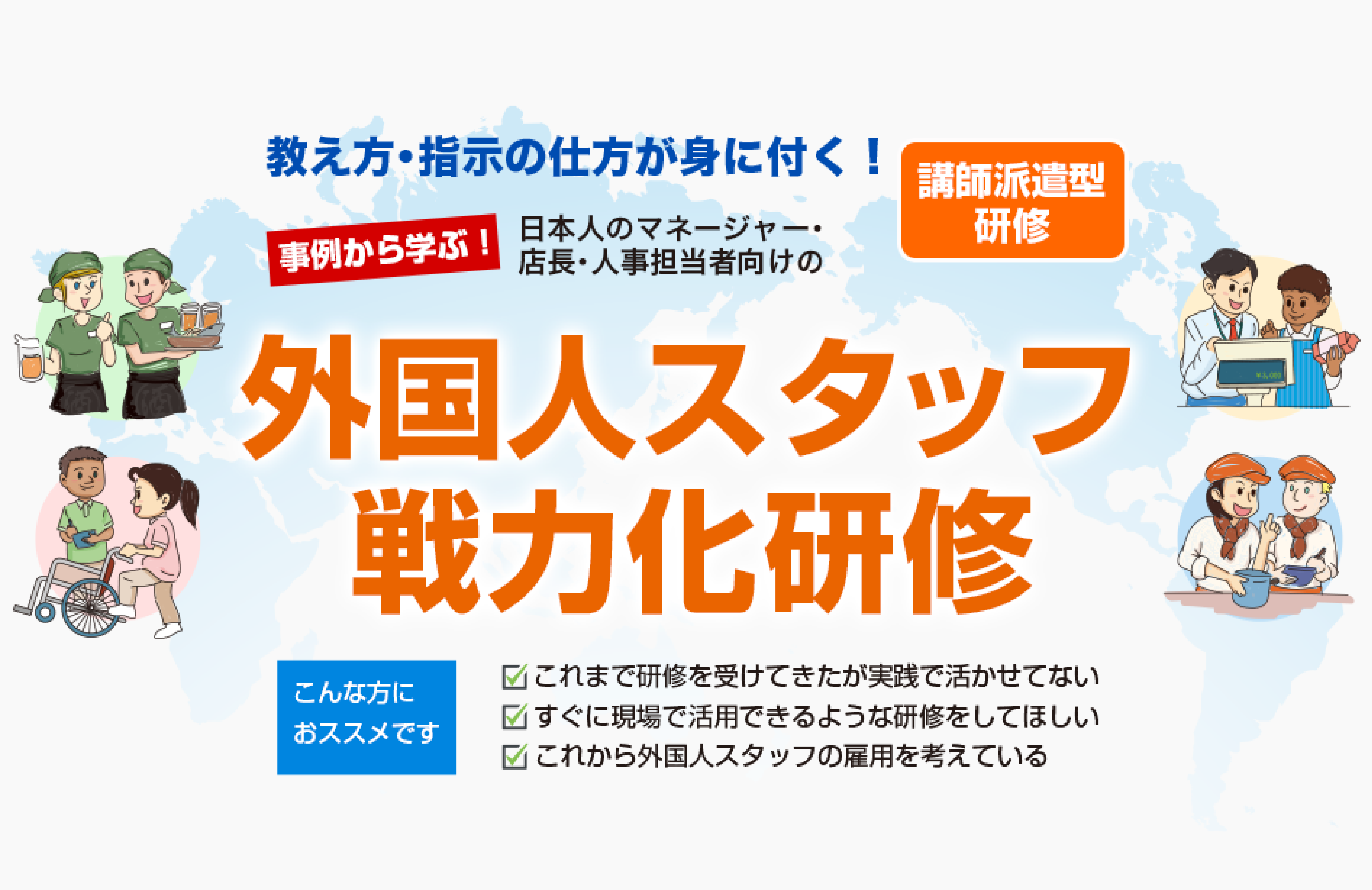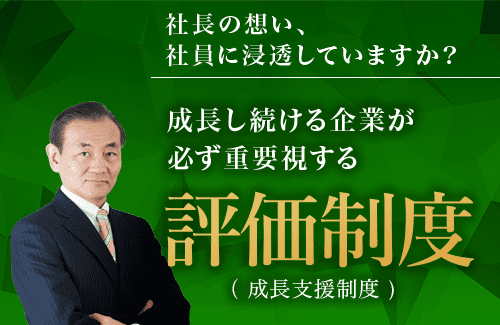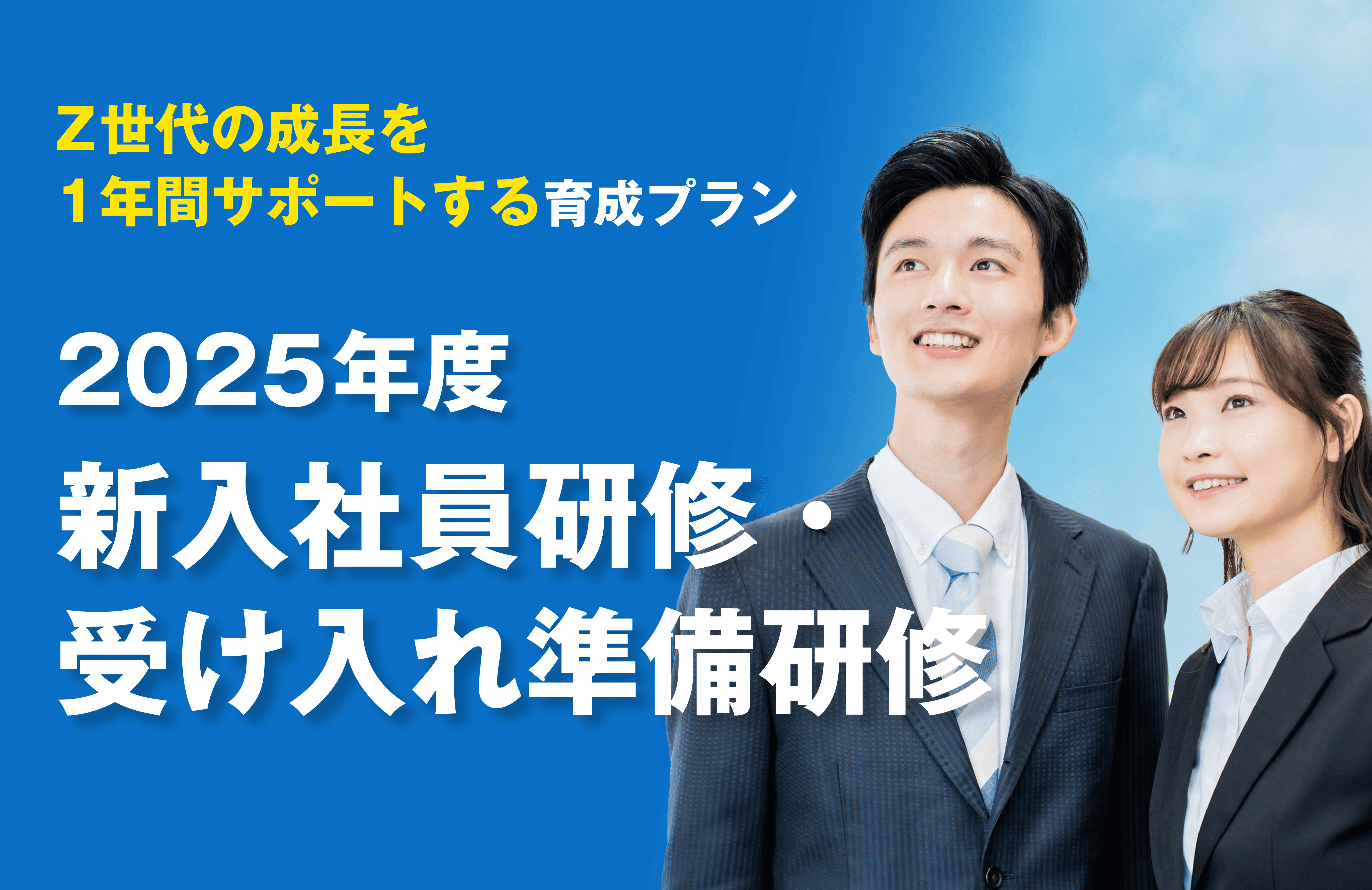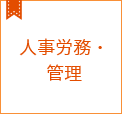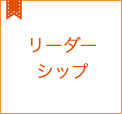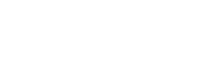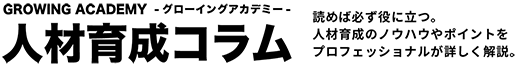- Home
- 離職防止, ニュース(人財/人事関連), お役立ちコンテンツ
- 企業と職場のメンタルヘルス対策総まとめ 今すぐ始めるメンタルヘルス対策|重要性や具体例を紹介
企業と職場のメンタルヘルス対策総まとめ 今すぐ始めるメンタルヘルス対策|重要性や具体例を紹介
- 2025/4/25
- 離職防止, ニュース(人財/人事関連), お役立ちコンテンツ

目次 こちらをクリックすると詳細を表示・非表示できます
- 1.はじめに:なぜ今メンタルヘルス対策が重要なのか?
- 1-1.職場におけるメンタル不調が増加する背景
- 1-2.メンタルヘルス対策の重要性
- 1-3.企業と個人が共に向き合うべき課題
- 2.メンタルヘルスとは?基本理解と不調のサイン
- 3.職場におけるメンタルヘルス不調の現状と原因
- 4.企業がメンタルヘルス対策に取り組む理由とメリット
- 4-1.法的義務(労働安全衛生法・ストレスチェック)
- 4-2.健康経営との連動
- 4-3.離職率やミスの防止、企業価値向上の可能性
- 4-4.労災リスク・ハラスメント訴訟の防止
- 5.メンタルヘルス対策の基本方針:4つのケアとは
- 6.メンタルヘルス対策の3つの予防段階
- 6-1.一次予防:未然防止
- 6-2.二次予防:早期発見・対応
- 6-3.三次予防:復職支援と再発防止
- 7.メンタルヘルス対策を成功させるポイント
- 7-1.組織全体での理解と継続的な推進
- 7-2.経営層・担当者・従業員それぞれの役割
- 7-3.外部専門家との連携・社内体制の整備
- 7-4.義務化で終わらせない“文化”としての定着
- 8.企業における具体的なメンタルヘルス対策
- 9.他企業の実践事例に学ぶ:成功するメンタルヘルス施策
- 10.個人でできるセルフケアと社内の取り組み
- 10-1.日常的なメンタルケアのコツ(深呼吸、ストレッチ、趣味など)
- 10-2.スマホアプリやマインドフルネスの活用
- 10-3.チーム内で支え合う仕組みづくり
- 11.まとめ:今日からできる一歩を
1.はじめに:なぜ今メンタルヘルス対策が重要なのか?
1-1.職場におけるメンタル不調が増加する背景
近年、職場でのメンタルヘルス不調を訴える従業員が増加しています。過重労働や人間関係のストレス、働き方の多様化による孤立感などが要因として挙げられます。特にコロナ禍以降、リモートワークや職場環境の変化がもたらす不安や孤独が顕著になりました。こうした背景のもと、企業には従業員の心の健康に対する理解と支援が強く求められています。
1-2.メンタルヘルス対策の重要性
メンタルヘルス対策は、単なる一時的な配慮ではなく、企業経営に不可欠な施策となりつつあります。従業員の心の不調は、生産性の低下や離職率の上昇、事故や訴訟リスクなど多くの課題に直結します。本記事では、メンタルヘルス対策の基本から実践的な取り組みまで、企業と個人の両面から包括的に解説していきます。
1-3.企業と個人が共に向き合うべき課題
メンタルヘルスは企業が一方的に取り組むものではありません。組織と従業員、双方が協力し合い、心の健康を守る文化を醸成することが重要です。企業は環境整備や支援体制の構築を進め、従業員は自身の状態を理解し、セルフケアを実践する必要があります。両者の協働こそが、持続可能な健康経営の鍵となります。
2.メンタルヘルスとは?基本理解と不調のサイン
2-1.メンタルヘルスの定義(WHOの定義含む)
メンタルヘルスとは、単に精神的な病気がない状態を指すのではありません。WHO(世界保健機関)では、メンタルヘルスを「自分の能力を発揮し、日常のストレスに対処し、生産的に働き、社会に貢献できる心の状態」と定義しています。つまり、心の健やかさとは、生活と仕事に前向きに向き合える土台を意味します。
2-2.心の健康=病気がない状態ではない
心の健康は、身体の健康と同じく、日々のメンテナンスが必要です。見た目に異常がなくても、慢性的なストレスや不安を抱え続けると、心は静かに疲弊していきます。「元気そうに見える=健康」とは限らず、メンタルの不調は外からは見えにくいため、周囲の理解とセルフモニタリングが欠かせません。
2-3.代表的なメンタル不調(うつ病、適応障害など)
職場でよく見られるメンタル不調には、うつ病や適応障害、不安障害などがあります。初期段階では、無気力や集中力の低下、眠れない・朝起きられないといった身体的症状が現れます。放置すると、休職や離職に至るケースも少なくありません。早期発見と適切な対応が、回復への第一歩となります。
2-4.不調に気づくポイントと早期発見の重要性
「最近、いつも疲れている」「些細なことで落ち込む」「笑顔が減った」など、普段と異なる様子はメンタル不調のサインかもしれません。本人が気づきにくい場合も多いため、上司や同僚が違和感に気づき、声をかけることが重要です。早期に対応すれば、回復も早く、職場全体の負担も軽減できます。
3.職場におけるメンタルヘルス不調の現状と原因
3-1.調査・統計から見る不調の割合
厚生労働省の調査によると、仕事や職業生活で強い不安やストレスを感じている労働者は全体の半数以上にのぼります。2022年11月〜2023年10月の1年間で、メンタルヘルス不調により「1か月以上の休業」または「退職者」がいた事業所は全体の13.5%になります。
ストレスチェックを行った事業所のうち、部署ごとなどの集団分析を実施したのは約69%。その中で、実際に分析結果を職場改善などに活用した事業所は約78%にのぼりました。
特に20〜40代では、メンタル不調による休職や離職も増加傾向にあります。こうした統計からも、職場のメンタルヘルス対策は「必要不可欠な施策」と言えるでしょう。
参考:令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/r05-46-50_gaikyo.pdf
3-2.主な原因:業務負担、人間関係、職場環境、ハラスメント等
メンタル不調の背景には、長時間労働や過剰な業務負担が大きく関わっています。さらに、上司や同僚との人間関係の悪化、パワハラ・セクハラなどのハラスメントも深刻な要因です。職場環境が悪化すれば、従業員の心理的安全性は損なわれ、心身の不調を引き起こしやすくなります。
3-3.ストレス・不安・孤立の実態
近年ではテレワークの普及によって、業務効率が向上した一方で「孤独感」や「相談しづらさ」によるストレスも増えています。上司や同僚とのコミュニケーション不足が心理的な距離を生み、孤立を深めてしまうケースも見られます。こうした状況は、メンタル不調の温床になり得ます。
3-4.社員・従業員への悪影響(生産性低下・退職リスクなど)
心の不調は、集中力や判断力の低下を招き、仕事の質にも影響します。結果として、業務ミスの増加や生産性の低下が起こり、チーム全体にも悪影響を及ぼします。さらに、未対応のまま放置すれば、従業員の離職や休職リスクが高まり、企業の人材損失にもつながります。
4.企業がメンタルヘルス対策に取り組む理由とメリット
4-1.法的義務(労働安全衛生法・ストレスチェック)
2015年の労働安全衛生法の改正により、従業員50人以上の事業場ではストレスチェック制度の実施が義務化されました。企業はこれにより、従業員のメンタル状態を把握し、必要に応じた措置を講じる責任があります。この法的義務は、職場の心の健康を「管理すべき対象」として明確化したものです。
参考:ストレスチェック制度について(厚生労働省)
https://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou/
4-2.健康経営との連動
近年注目されている「健康経営」とは、従業員の健康を経営的視点からとらえ、戦略的に管理・改善する取り組みです。メンタルヘルス対策は、心身の健康維持を通じて業務パフォーマンスを高め、組織全体の活力を生む要素として位置づけられます。企業価値を高める投資としても非常に有効です。
4-3.離職率やミスの防止、企業価値向上の可能性
メンタル不調の未対応は、従業員の離職や業務ミスにつながり、職場全体の士気低下を招きます。反対に、対策を講じることで従業員のエンゲージメントが高まり、離職率や事故の発生率が低減します。結果として、企業の社会的信用やブランド価値の向上にも寄与することができます。
4-4.労災リスク・ハラスメント訴訟の防止
メンタル不調が深刻化すると、労働災害として労災認定されるリスクがあります。また、ハラスメントや安全配慮義務違反による訴訟のリスクも無視できません。企業が適切な対策を講じ、相談体制を整えることは、法的トラブルの予防にもつながります。未然に防ぐ体制整備が企業防衛の一環となります。
5.メンタルヘルス対策の基本方針:4つのケアとは
5-1.厚生労働省が示す「4つのケア」モデル解説
厚生労働省は、職場におけるメンタルヘルス対策の基本方針として「4つのケア」を提唱しています。これは、セルフケア・ラインケア・産業保健スタッフによるケア・事業場外資源によるケアの4つで構成され、従業員本人から管理職、専門家、外部機関まで幅広い立場が連携して心の健康を守る考え方です。
参考:メンタルヘルスの4つのケアってなんだろう?(厚生労働省)
https://kokoro.mhlw.go.jp/usagi/ug008/
1. セルフケア
セルフケアとは、従業員自身がストレスや体調の変化に気づき、適切に対処する力を養うことです。十分な休養、バランスの良い食事、運動、睡眠の確保、趣味の時間などが有効とされています。企業は従業員に向けて、セルフケアに関する知識の提供や、研修・資料配布などを通じて実践を後押しする必要があります。
2. ラインケア
ラインケアは、職場の上司や管理監督者が担うケアのことです。部下の日常の変化に早く気づき、声をかけたり、業務調整を行ったりすることが含まれます。コミュニケーションの促進や、相談しやすい雰囲気づくりが大切です。管理職自身のストレス対処力を高めるための教育や支援も必要です。
3. 産業保健スタッフによるケア
産業医や保健師、衛生管理者、人事労務スタッフなどが行うのがこのケアです。従業員の相談対応、ストレスチェック結果の分析、職場復帰支援、研修の実施などが主な役割です。従業員が安心して相談できる専門的な体制を整えることは、組織全体のメンタルヘルス向上に直結します。
4. 事業場外資源の活用(EAP、支援センター等)
社内だけで対応が難しい場合は、外部の専門機関を活用することも重要です。EAP(従業員支援プログラム)や産業保健総合支援センター、地域の相談機関などがその例です。専門的なカウンセリングや研修の提供を通じ、従業員の心のケアを多面的に支援することが可能になります。
6.メンタルヘルス対策の3つの予防段階
メンタル不調への対応は段階的な予防が基本
メンタルヘルス対策は、単に不調者への対応にとどまりません。厚生労働省では、一次予防(未然防止)、二次予防(早期発見)、三次予防(再発防止)の3段階に分けた取り組みを推奨しています。段階的に対策を講じることで、職場全体のリスクを大幅に低減することができます。
6-1.一次予防:未然防止
一次予防は、不調が起こる前にその発生を防ぐ取り組みです。具体的には、職場環境の改善、業務量の適正化、ハラスメント防止、良好な人間関係づくりなどが該当します。さらに、ストレスに関する正しい知識を従業員に伝える研修や、セルフケア教育も一次予防に含まれます。
6-2.二次予防:早期発見・対応
二次予防は、不調の兆しを早期に見つけ、速やかに対応することを指します。ストレスチェック制度の導入・実施、管理職による日常的な観察、社内相談窓口の設置と周知などが代表的な手法です。早期に発見すればするほど、従業員の負担は軽く、職場への影響も最小限に抑えられます。
6-3.三次予防:復職支援と再発防止
三次予防では、すでに休職している従業員の復職支援と、再発防止が主な目的となります。復職前の面談、リワークプログラム、短時間勤務の活用など、段階的な支援が重要です。また、復帰後の継続的なフォローと職場との連携により、再発のリスクを抑え、安心して働き続けられる環境を整えることが求められます。
7.メンタルヘルス対策を成功させるポイント
7-1.組織全体での理解と継続的な推進
メンタルヘルス対策は、一部の担当者だけで完結するものではありません。経営層から一般社員まで、組織全体がその重要性を理解し、共通の認識を持つことが不可欠です。また、一度の施策で終わらせず、継続的な取り組みとして社内文化に根づかせることが、長期的な効果を生みます。
7-2.経営層・担当者・従業員それぞれの役割
経営層は、対策を経営戦略の一環として明確に示し、予算やリソースを確保する責任があります。担当者は制度設計と運用、従業員はセルフケアの実践や相談の活用など、立場ごとに果たすべき役割があります。それぞれが自分の役割を理解し、行動することで、健全な職場環境が育まれます。
7-3.外部専門家との連携・社内体制の整備
社内リソースだけでは限界があるため、外部の専門家と連携する体制も重要です。産業医やカウンセラー、EAP、支援センターなどを活用することで、専門的な知識と中立的な対応が可能になります。また、相談体制や復職支援制度をマニュアル化し、誰もが安心して使えるよう整備しておくことが望まれます。
7-4.義務化で終わらせない“文化”としての定着
ストレスチェック制度などの法的義務を「やらされ仕事」で終わらせるのではなく、メンタルヘルス対策を“企業文化”として定着させることが理想です。日常の中に自然とケアが根づくよう、風通しの良い環境づくりや、前向きなコミュニケーションの風土を醸成していくことが鍵になります。
8.企業における具体的なメンタルヘルス対策
8-1.社内制度や体制づくり(相談窓口、外部連携、規程整備)
メンタルヘルス対策を定着させるには、制度や体制の整備が不可欠です。具体的には、社内相談窓口の設置、外部機関との連携体制の構築、ハラスメント防止規程やメンタル不調時の対応マニュアルの明文化などが求められます。誰もが安心して相談できる仕組みが、信頼と安全の職場づくりにつながります。
8-2.セミナー・研修・社内イベントの開催
従業員の意識向上やスキルアップのためには、定期的なセミナーや研修の実施が効果的です。セルフケア講座や管理職向けのラインケア研修、ストレスマネジメントセミナーなどを社内イベントとして組み込むことで、従業員の関心と参加意識を高めることができます。メンタルヘルスの啓発にもつながります。
8-3.データに基づく継続的な効果測定
施策を実施するだけでなく、その効果を継続的に検証することも重要です。ストレスチェックの結果分析や、研修参加率・相談件数などのデータをもとに、対策の有効性を数値で把握します。定期的なPDCA(計画→実行→評価→改善)の運用が、より実効性のある対策へとつながります。
8-4.「健康メンタル環境向上プロジェクト」や各種補助金の活用
国や自治体では、企業向けにメンタルヘルス支援のための補助制度を用意しています。たとえば令和6年度 団体経由産業保健活動推進助成金は中小企業などを支援する団体が、産業医や保健師などによる産業保健サービスを提供した場合、その費用の一部が助成される制度です。専門職との契約を通じた健康支援活動が対象です。
外部リソースや補助金を賢く活用することで、コストを抑えながら質の高い対策が実現できます。
参考:助成制度(厚生労働省)
https://kokoro.mhlw.go.jp/support/
9.他企業の実践事例に学ぶ:成功するメンタルヘルス施策
【実例紹介①】ダイトーケミックス株式会社のメンタルヘルス対策
ダイトーケミックス株式会社では、産業看護師が従業員の健康診断やストレスチェックの結果を把握し、“立ち話面談”を通じて日常的に小さな変化を見逃さない健康管理を実施しています。セルフケア・ラインケア・産業保健スタッフによるケアに加え、同僚同士の声かけによる“同僚ケア”も機能しており、メンタル不調による休業者はほとんどいません。さらに、健康経営推進委員会を立ち上げ、禁煙推進、食生活改善、睡眠・運動習慣づくりなど、多面的な健康施策を全社的に展開。心身ともに健康で働ける職場づくりを実現しています。
参考:ダイトーケミックス株式会社(大阪府大阪市)(厚生労働省)
https://kokoro.mhlw.go.jp/case/company/cmp147/
【実例紹介②】株式会社コー・ワークスのメンタルヘルス対策
株式会社コー・ワークスでは、社内外の公認心理師による体制を整備し、全社員を対象に年2回のストレスチェックと全員面談を実施。従業員数が50名未満で義務がない中でも、自社の課題を的確に把握し、職場環境の改善に活かしています。毎日の朝会や月1回の全社連絡会を通じた丁寧な対話に加え、自社開発の「ココケア」アプリを活用し、気軽に相談できる仕組みも構築。継続的な発信と対話を重ねることで、従業員のエンゲージメント向上とメンタル不調の早期発見・予防を実現しています。
参考:株式会社コー・ワークス(宮城県仙台市)(厚生労働省)
https://kokoro.mhlw.go.jp/case/company/cmp142/
10.個人でできるセルフケアと社内の取り組み
10-1.日常的なメンタルケアのコツ(深呼吸、ストレッチ、趣味など)
メンタルケアは、特別なことではなく日々の小さな習慣から始まります。たとえば、1分間の深呼吸やストレッチ、好きな音楽を聴く、趣味に没頭する時間を意識的に作ることなどが効果的です。自分に合った方法で、心をほぐす時間を日常に取り入れることが、不調の予防につながります。
10-2.スマホアプリやマインドフルネスの活用
最近では、メンタルヘルス支援を目的としたスマホアプリも多く登場しています。マインドフルネス瞑想や睡眠改善、感情記録などの機能を活用することで、セルフケアがより手軽に実践できます。アプリは忙しいビジネスパーソンにとって、自己管理を習慣化する強力なツールとなります。
10-3.チーム内で支え合う仕組みづくり
個人のセルフケアに加えて、職場全体で支え合う仕組みづくりも大切です。たとえば、朝礼での体調共有や、定期的な1on1面談、ピアサポート制度の導入などが有効です。互いの変化に気づき、声をかけ合える職場風土が、メンタルヘルス不調の早期発見と予防につながります。
11.まとめ:今日からできる一歩を
本記事では、職場におけるメンタルヘルス対策の基本から、実践事例、個人のセルフケアまでを幅広くご紹介しました。企業としての体制整備、管理職の関わり、外部機関との連携など、段階的かつ総合的な対策が求められます。これらを継続的に実施することが、健康で持続可能な組織の基盤となります。
働く人の心が健康であってこそ、企業は本当の意味での成長を遂げられます。メンタルヘルス対策は単なるコストではなく、未来への投資です。今日できる小さな一歩を大切に、心と職場の健やかな循環を目指していきましょう。
■ 関連資料・相談窓口の紹介
厚生労働省が運営する「こころの耳」(https://kokoro.mhlw.go.jp/)や「産業保健総合支援センター」(https://www.johas.go.jp/shisetsu/tabid/578/Default.aspx)など、信頼できる情報源や相談先を積極的に活用しましょう。また、社内の相談窓口が設置されている場合は、その存在を再確認し、気軽にアクセスできる雰囲気づくりが大切です。
関連するサービス